ハイドロカルチャーの日常管理!水やりの方法と注意点

この記事では、観葉植物の室内専用育成方法ハイドロカルチャー(水耕栽培)の日常管理「水やり」について解説します。
ハイドロカルチャーの水やりは、通常の花壇や土の鉢植えとは違い、独特の管理が必要です。
通常の花壇や土の鉢植えは、上から水をたっぷりかけるだけですが、ハイドロカルチャーは難しそうと思ったことはありませんか?
ハイドロカルチャーの水やりは、あたえる水の量や間隔など気をつけるポイントがいくつかあります。
植物を育てる日常管理の代表格「水やり」の基本的な方法とおすすめの添加剤、「水やり」にまつわるトラブルの対処方法などを解説します。
ハイドロカルチャーの水やり方法
ハイドロカルチャーで育てる場合は、土植えの鉢とは違い水捌け用の穴が空いていない容器を使います。土植えの植木鉢であればあたえすぎた水は鉢底の穴から流れていき、常に適切な量の湿度を土がたもってくれますが、ハイドロカルチャーは植物が水を吸い上げてしまうまで、容器の底に貯まり続けます。
必要以上にあたえすぎると根腐れを起こして枯れてしまうこともあるため、あたえる水の量は細かく管理して上げる必要があります。
あたえる水の量
ハイドロカルチャーで育てる植物にあたえる水の量は、植物の種類や育成状態(大きさ)によって変わってきます。一般的によく耳にするのは、容器の底から1/5〜1/3程度あたえるというものです。
植物の種類も大きさも違うのに、なぜ容器の底から1/5〜1/3程度と言われているのか不思議に思いませんか?
その理由は、水をあたえてからおよそ3〜5日程度で植物が水を吸い上げ、鉢底の水がなくなるくらいの分量を目安にしているからです。
 taks
taksハイドロカルチャーの水やりで一番怖い失敗は、水のあたえ過ぎで根が長期間水に浸かったままになり、根腐れすることです。
植物の根腐れを防ぐには、水に浸かっている期間が3〜5日程度で終わるようにしてあげます。鉢底の水がなくなったあと、根を空気に触れさせて呼吸をさせる必要があります。
植物の根も呼吸をしていますので、水に浸かったままだと窒息します。鉢底の水がなくなった後は、数日をかけてセラミスなどの支持材に染み込んだ水を吸収しながら酸素を取り入れて呼吸しています。
ハイドロカルチャーで育てる植物にあたえる水の量は、およそ3〜5日程度で植物が水を吸い上げ、鉢底の水がなくなるくらいの分量あたえてください。
水やり頻度・間隔
ハイドロカルチャーで育てる植物の水やり間隔は、鉢底の水がなくなったあと、支持材に染み込んだ水を吸収しながら酸素を取り入れて呼吸しているため、鉢底の水がなくなってから1〜3日開けて次をあたえます。
この期間は、植物によって大きく変わってきます。水を好む植物は、完全に水が乾くとすぐに葉先が枯れだすため、支持材が完全に乾ききる前に次の水をあたえます。逆に乾いた場所を好む植物は、完全に乾くまで次をあたえてはいけません。
 taks
taks植物が水を好むのか乾いた場所を好むのか、よくわからないこともあります。例外もありますが簡単な判断基準として、根が太い植物ほど乾燥に強く、細い植物ほど水を好む傾向があります。
ここからは私の個人的な経験からの印象なのですが、例外として樹木系の植物は真逆のようです。エバーフレッシュやポリシャスなど根が細い木は、水を控えめにしたほうがよく根がのび育ちも良いです。
観葉植物の代表格的なパキラは、根は極太で乾燥にも強いという謳い文句で売られていますが、自生地は川岸などの水辺です。
最近育てているコーヒーの木は、根は中くらいの太さですが、乾燥気味に育てるとよく耳にします。しかしそれはコーヒー豆を栽培する時の話で、乾燥気味に育てたほうがコーヒー豆として味が凝縮され美味しくなるという農業の手法です。実際はとても水を好む植物のようです。
添加剤メネデールのすすめ
ハイドロカルチャーによる育成方法は、土植えとは違い支持材に一切栄養分がありません。植物は外部からあたえられる肥料や水からしか、必要な栄養を摂取することが出来ません。
肥料のあたえ過ぎは肥料やけを起こしてしまう可能性があるため頻繁にあたえることは出来ませんが、定期的にあたえる水には、活力剤のメネデールを入れています。
 taks
taksメネデールには発根や発芽を促す効果があるため、一般的に成長が遅いとされるハイドロカルチャーの植物には丁度よい添加剤です。
水やりの注意点
ハイドロカルチャーの水やりで気をつけるポイントを紹介します。
水の温度
ハイドロカルチャーで育てる植物は、あたえた水が直接根に触れます。外気温と極端に離れた温度にならないように注意が必要です。
夏の暑いときに蛇口から出たばかりの冷たい水をあたえたり、冬の寒いときに同じく蛇口から出たばかりのキンキンに冷えた水をあたえると植物にダメージをあたえてしまいます。
植物も生き物です。人がいきなり冷たいプールに飛び込むと心臓麻痺を起こすように、植物にとっても急激な温度変化はショックをあたえてしまいます。
自然界での水やりと言えば雨です。雨と同じように外気温とそれほど変わらない温度が、植物にとっては適温です。
 taks
taks水不足と根腐れの判断方法
水やりの失敗は、水不足による枯れはもちろんですが、水のあたえすぎによる根腐れにも注意が必要です。植物が調子を崩したとき、水不足によるものか根腐れかの判断基準を紹介します。
水不足・・・葉先や枝先など先端から枯れる。
根腐れ・・・葉の根元など植物本体の幹に近い側から枯れる。
植物は水不足になると水分の蒸発を最小限に抑えるため葉を落とします。
植物は根から水を吸い上げ、葉の裏側から蒸散させています。若い葉ほど蒸散の動きが活発なため、水不足によって枯れる場合、枝葉の先端側の葉先から枯れ始めます。
水不足の場合は、すぐに水を与えて日陰で休ませてあげます。
 taks
taks根腐れは酸素不足によって発生します。酸素が少ない状態を好む嫌気性菌が繁殖することで、根を腐蝕させるために起こります。
根の一部が腐蝕した初期の状態では、正常な根からは水を吸いあげることができるため葉先には影響ありませんが、腐蝕した根に近い葉から黄色く変色していきます。
水不足での枯れ葉と違い、枯れたように黄色く変色した葉にまだしっとりと水分が残っているにも関わらず、落ちてしまいます。
根腐れが進行してひどくなってくると、水を吸わなくなり幹部分がブヨブヨと柔らかくなったり腐敗臭がしてきます。根が腐り水も吸えなくなっているので、水不足の症状も合わせて出始めます。
 taks
taks根腐れは早期発見して、初期段階のうちに対処が必要です。
根腐れの初期症状を発見したら
- 容器内に水が残っている場合は水を捨てる。
- 水やりを控える。
- 容器内の水が完全に乾いてから2〜3日は水をあたえずにおいておく。
2〜3日経過後、通常通り水やりを開始して様子を見ます。
鉢内の水を完全に乾燥させることで酸素を鉢内に取り込み嫌気性菌を駆除します。嫌気性菌がいなくなると腐敗の進行が止まるので、水をあたえ新しく根を成長させるイメージです。
根腐れの進行具合によって、完全乾燥を数回行ったほうが良い場合もあります。根腐れで弱っているときに水不足はダメージが大きいので、容器内の水が完全に乾いて2〜3日放置後に水やりを数回繰り返します。
まとめ
ハイドロカルチャーで育てる植物への水やりは、メネデール入りの水を容器の底から1/5〜1/3程度(2〜3日でなくなる量)入れて、鉢底の水がなくなってから1〜3日経過してから次をあたえます。
水は植物の相手ある部屋と同じくらいの常温が基本です。常温保管したものを使いましょう。
水のあたえすぎにはとくに注意が必要で、植物の状態をよく観察して、元気がないときの判断を間違えないように対処しましょう。








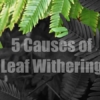

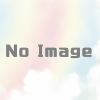

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません